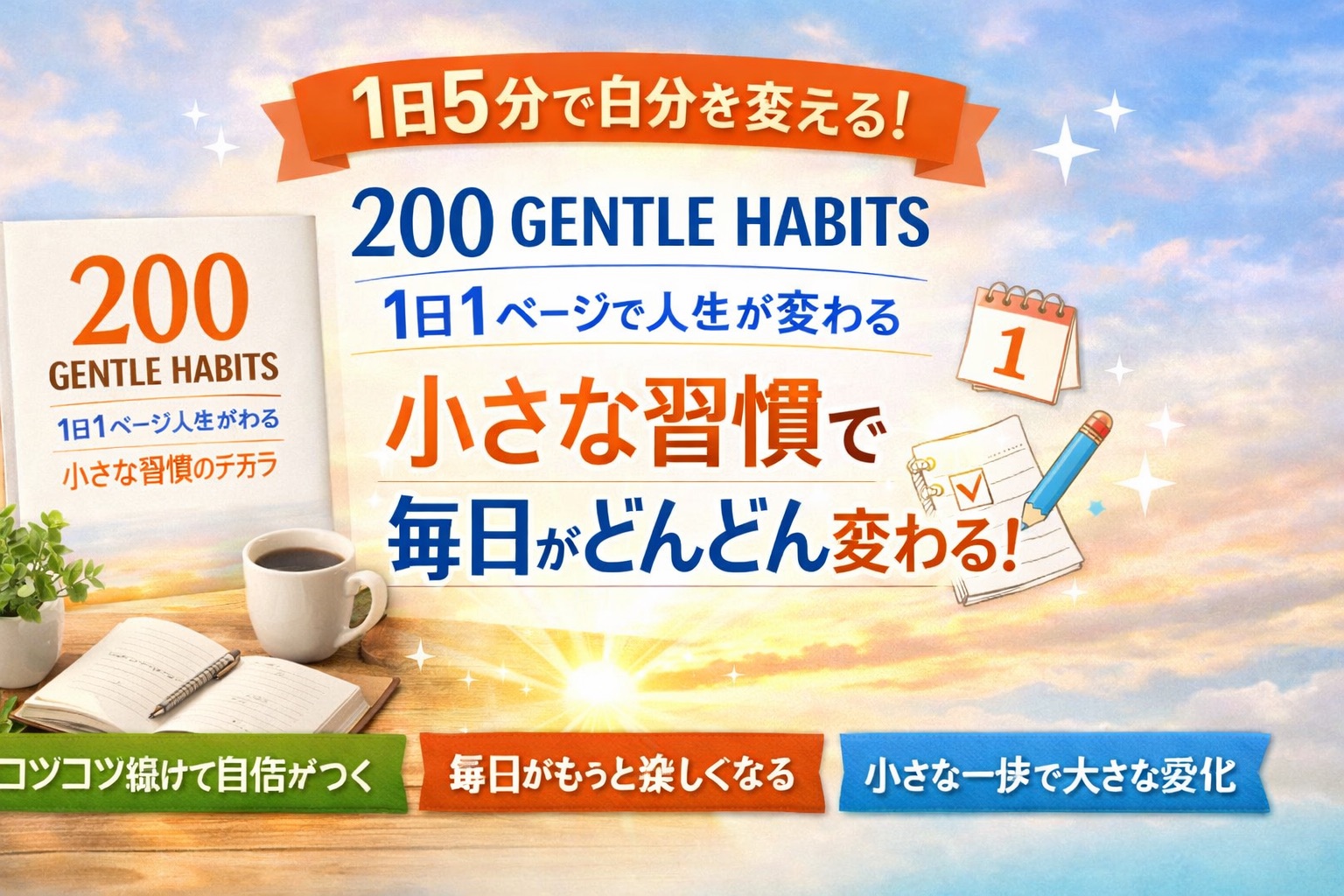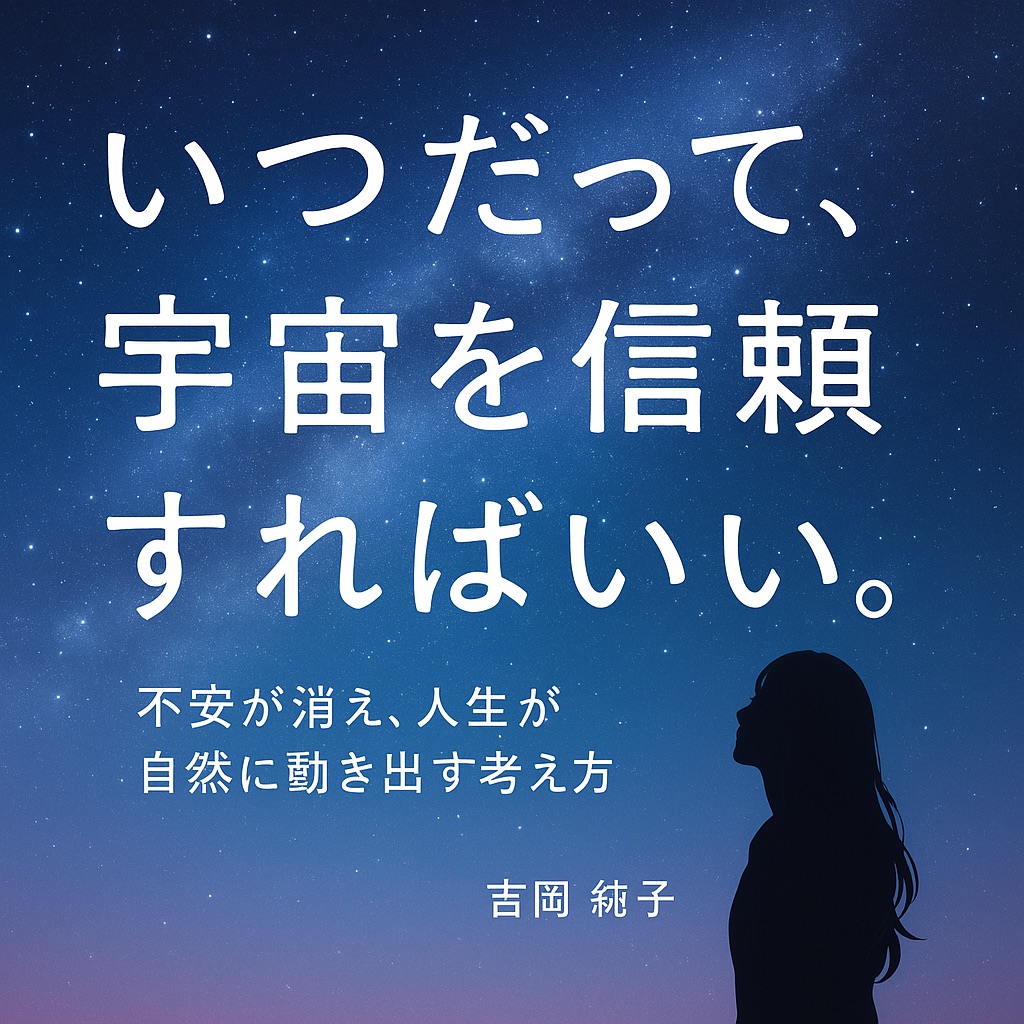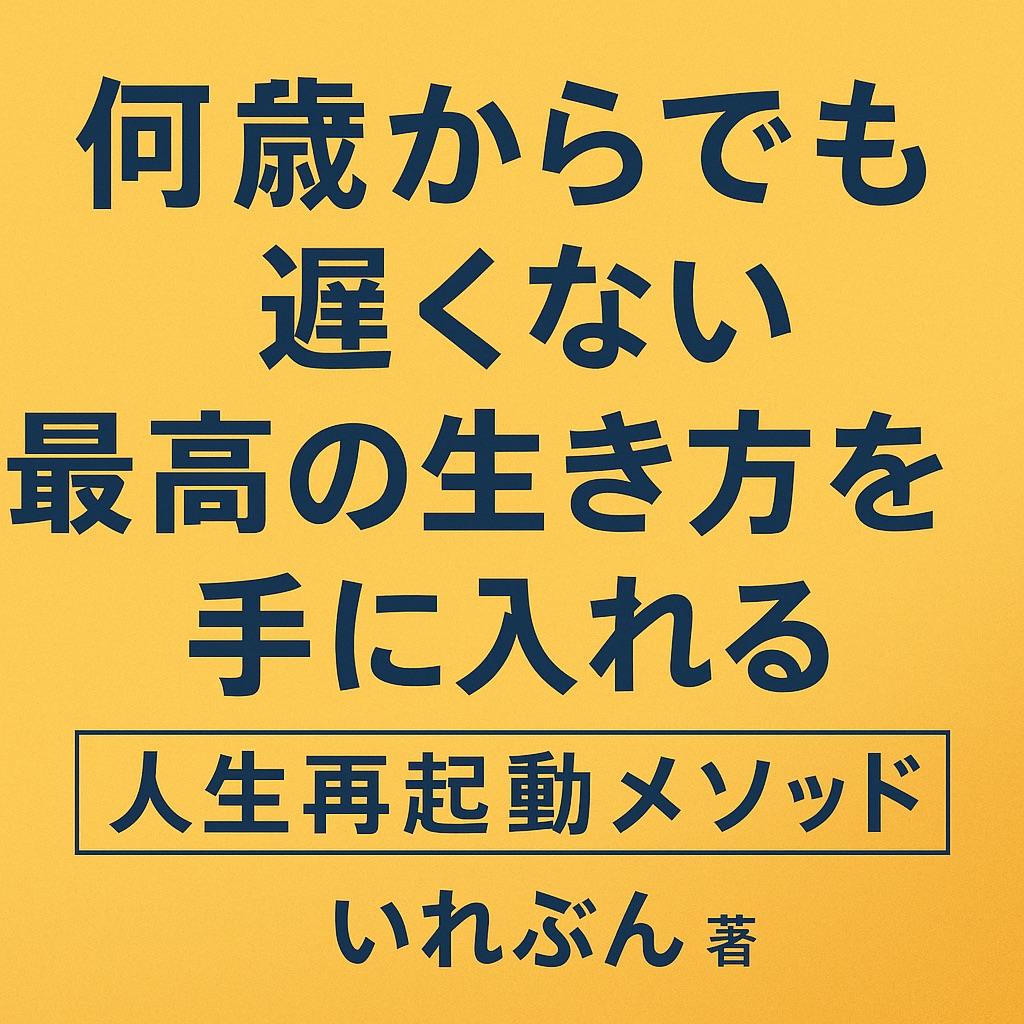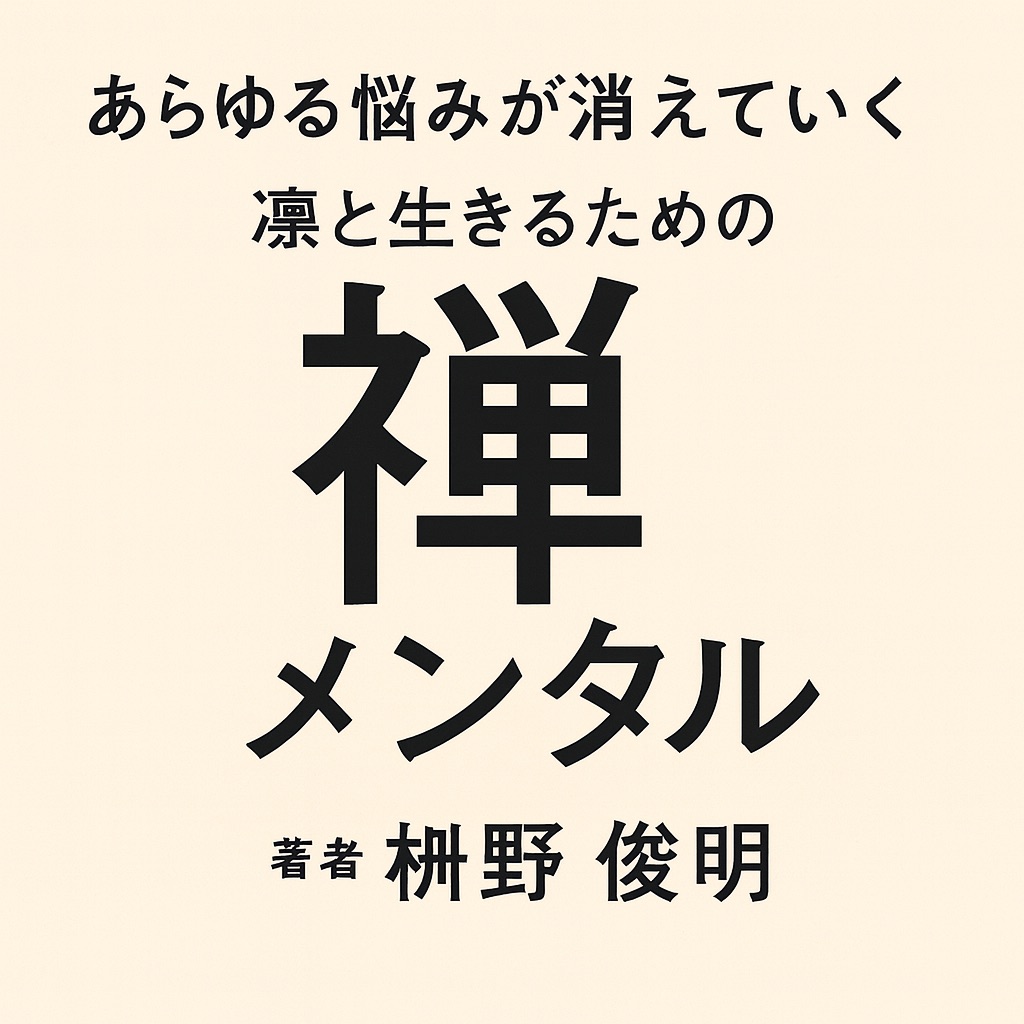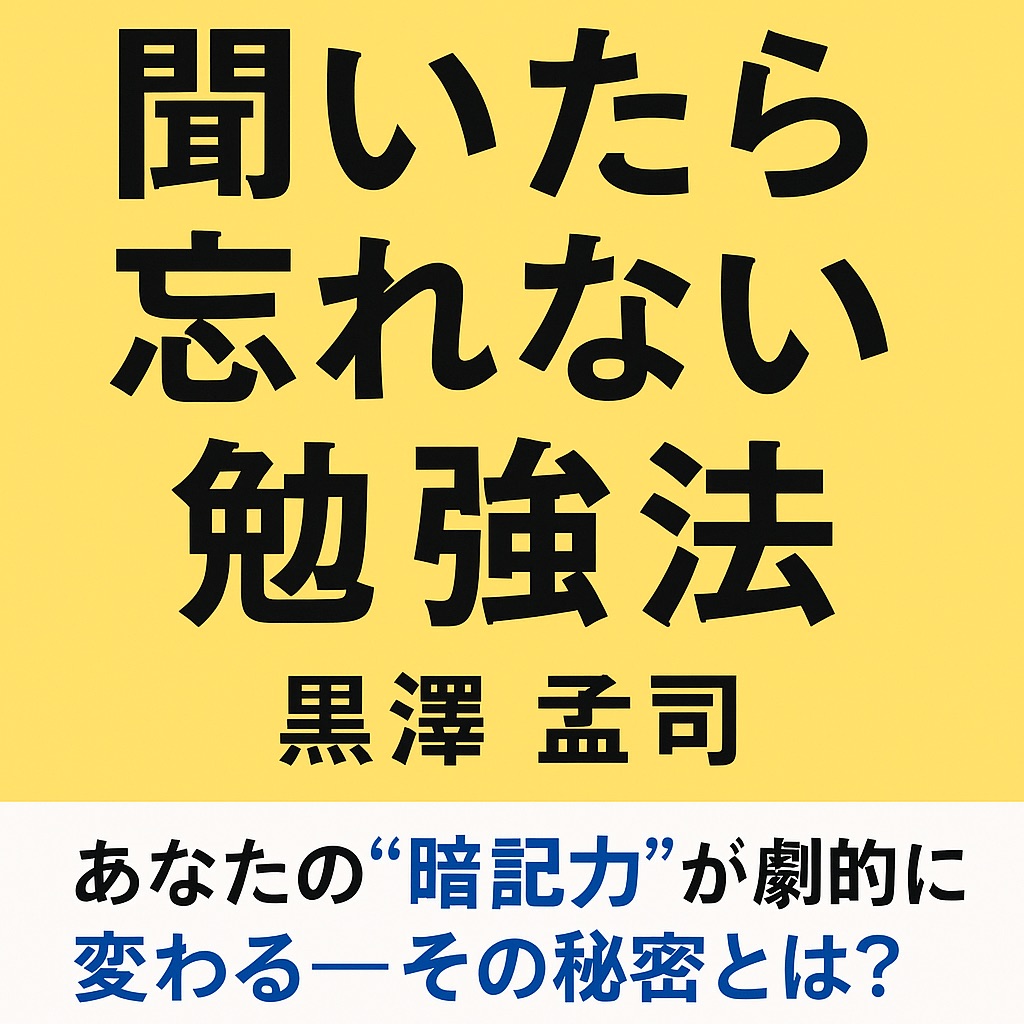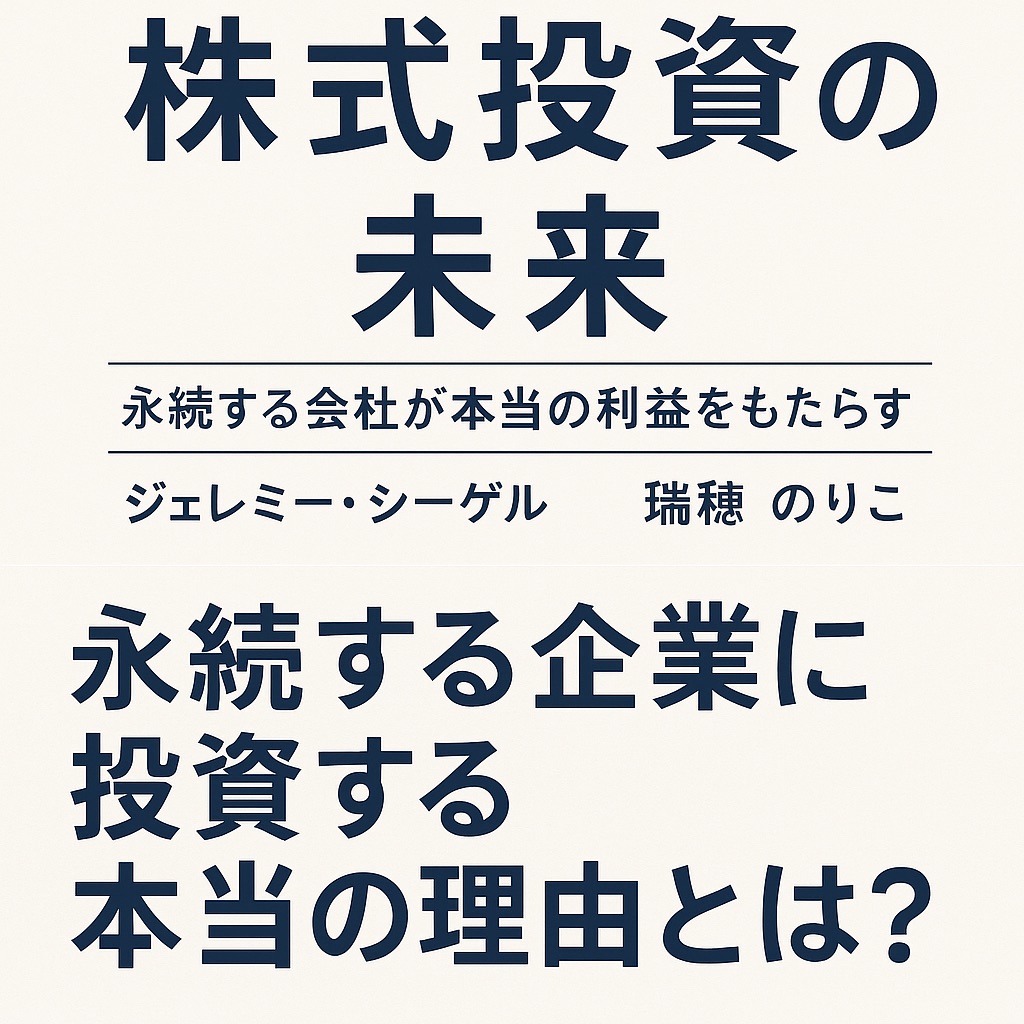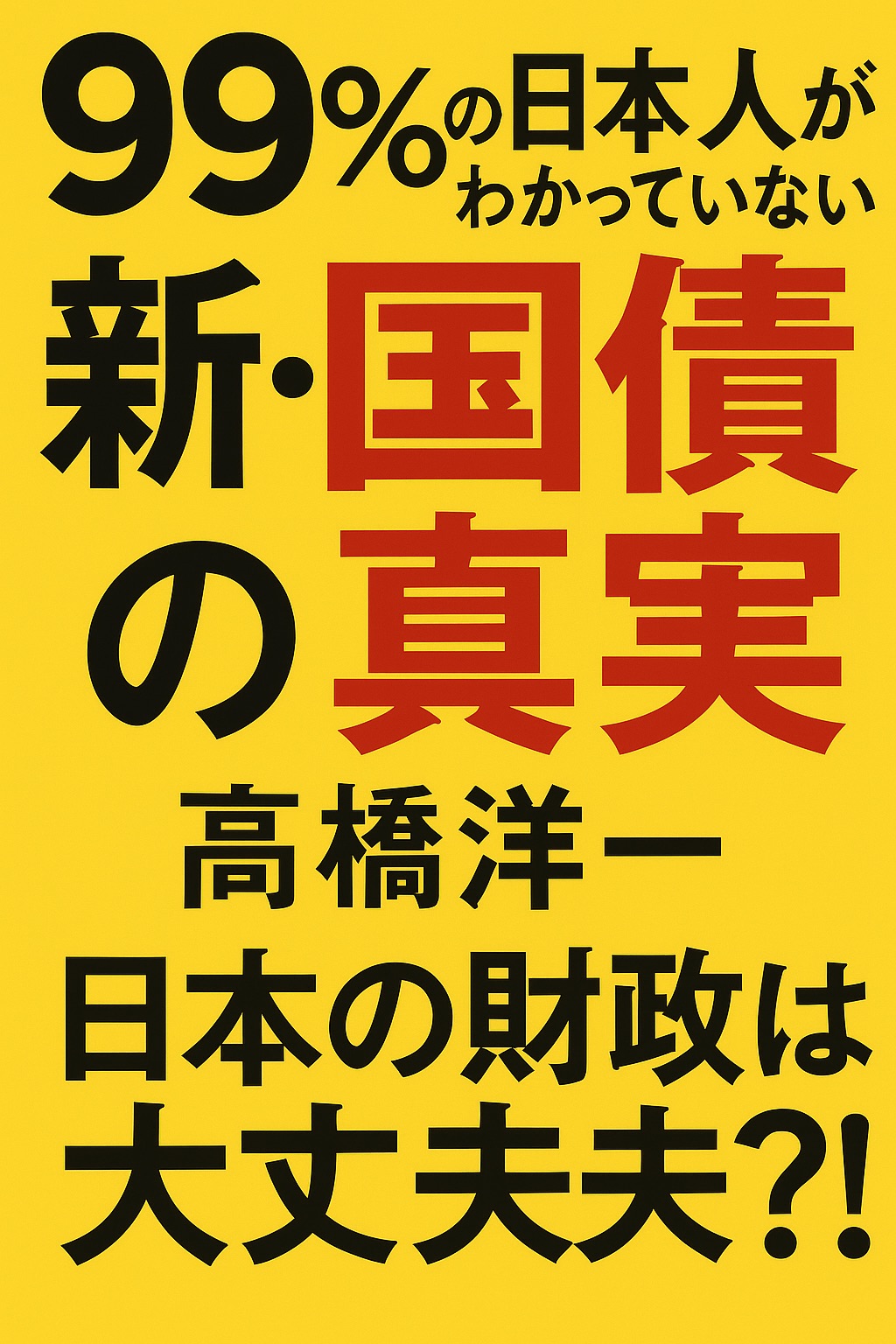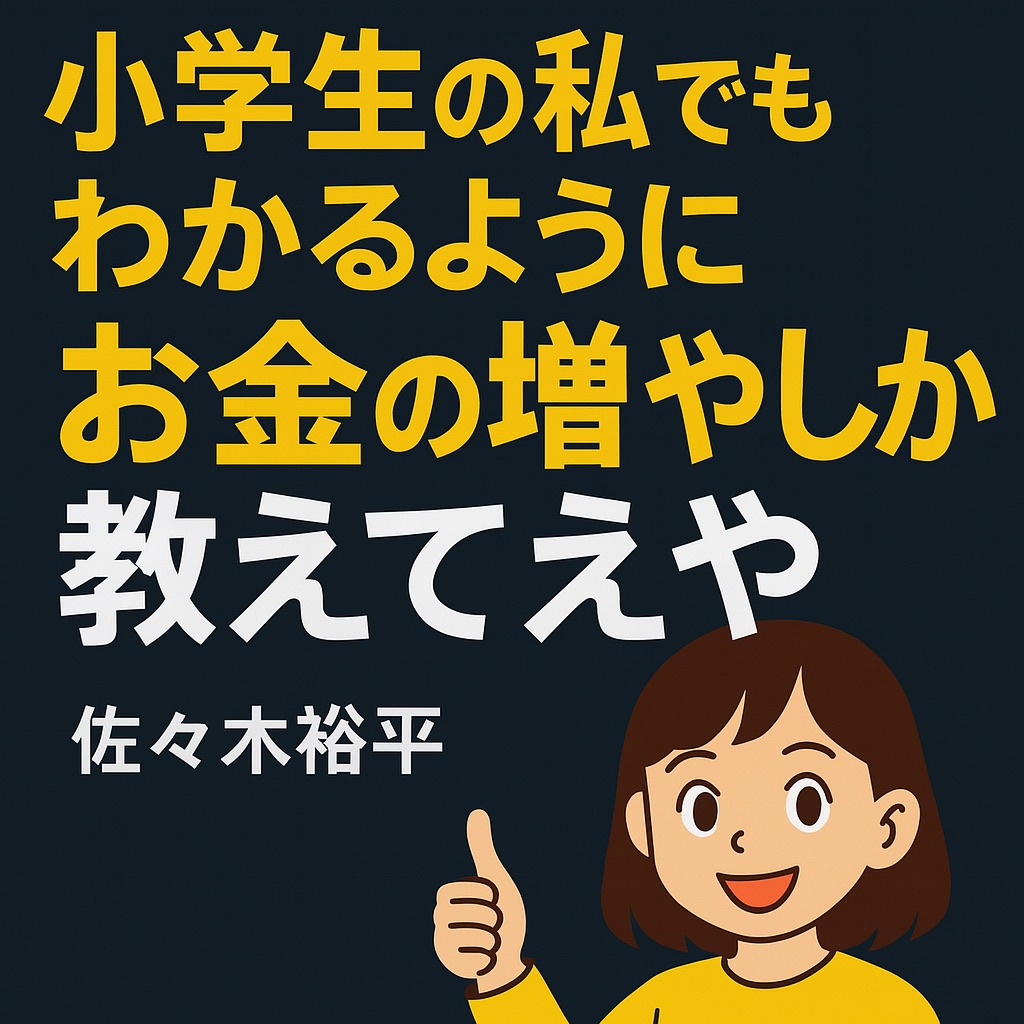【書評・感想】『MMTとケインズ経済学』現代日本経済の迷路を読み解く知的冒険
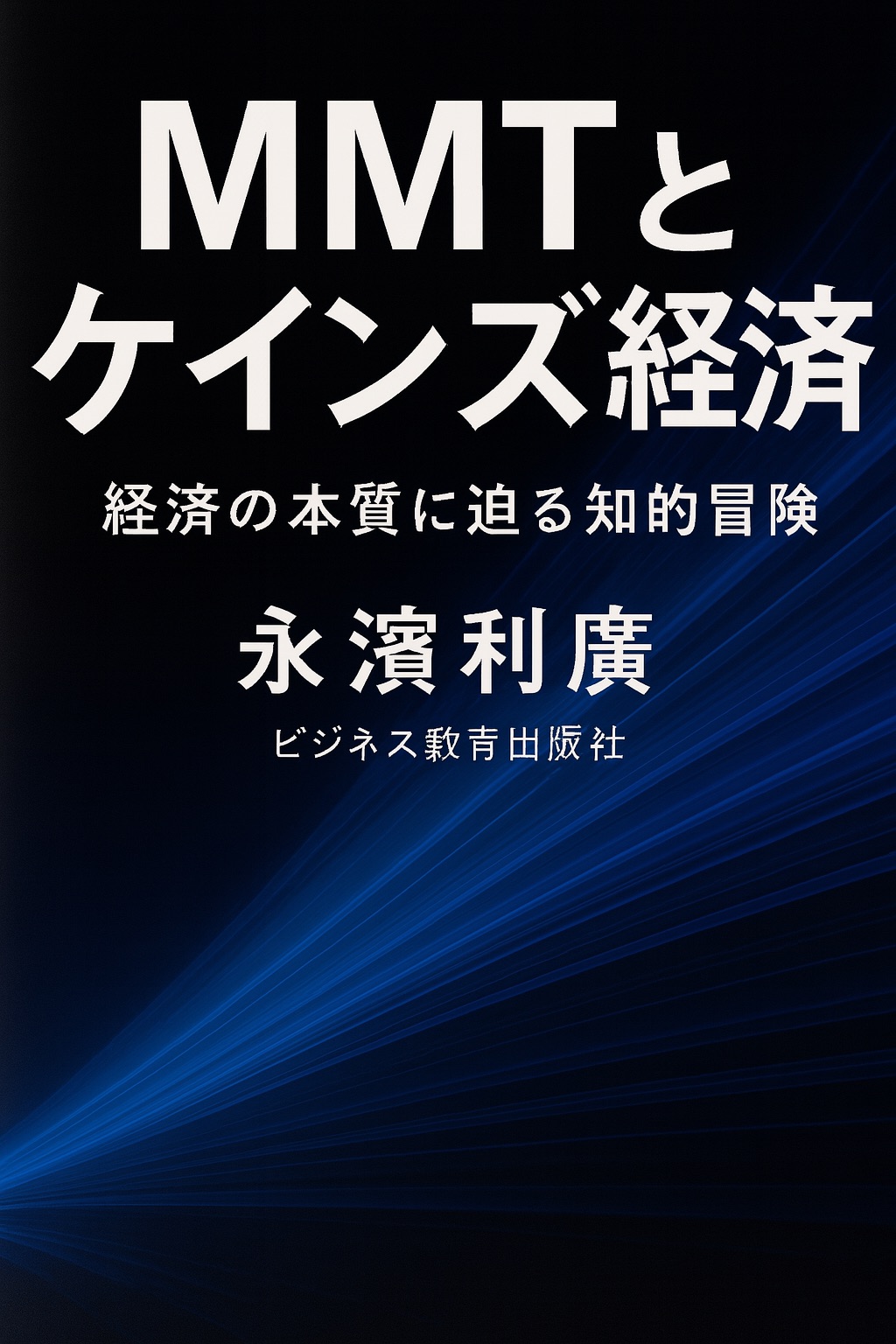
結論:日本経済の未来に必要なのは「恐れない財政」と「人間中心の政策」
経済という言葉を聞くだけで「難しそう」「専門的で分からない」と感じる方も多いはず。
でも、もしそれが自分たちの暮らしや未来と直結する大切な知識だったとしたら?
永濱利廣氏の著書『MMTとケインズ経済学』は、そんな「経済=難解」という壁を見事に取り払い、私たちの生活に密接に関わる経済政策について、やさしく、そして本質的に解説してくれる一冊です。
本書の最大の魅力は、「理論書」でありながら「人間味」があること。
経済をただの数字のやりとりとしてではなく、人が希望を持ち安心して生きるための“仕組み”として捉えている点が、非常に心に響きました。
本記事では、本書の魅力を以下の3つの視点から掘り下げながら、読後の気づきと学びをシェアしたいと思います。

1. MMT(現代貨幣理論)とは何か?経済の「前提」を問い直す視点
MMT(Modern Monetary Theory/現代貨幣理論)という言葉は、最近ニュースやSNSでも見かけることが増えました。
「政府は自国通貨を発行できるのだから、財政赤字を気にせず支出すべき」というこの理論には、正直なところ「本当にそんなことできるの?」という疑問が先に立ちます。
しかし、本書を読むと、そんな素朴な疑問に一つひとつ丁寧に答えが用意されていることに驚きます。
たとえば、
- お金とは何か?
- 政府と中央銀行の関係とは?
- なぜ財政赤字があっても破綻しないのか?
- インフレはどのように制御するのか?
こうした根源的な問いに対し、永濱氏は専門用語を噛み砕きながら、読者が腹落ちするまで説明してくれます。
特に印象に残ったのが、「お金は信用によって成り立つ」という指摘。
国民がその通貨や政府を信頼している限り、通貨が暴落することはない――これは、私たちが無意識に抱いていた「お金=モノ」的な認識を根底から覆す洞察でした。
つまり、お金の本質は「信頼」であり、財政赤字を恐れるよりも「政府の信頼性」をどう維持するかこそが重要。
これは、日本の財政議論における大きなパラダイム転換です。
2. ケインズとの対話:古典と現代の知をつなぐ
本書のもう一つの大きなテーマは、「MMTとケインズ経済学の比較」です。
ケインズといえば、1930年代の大恐慌に直面し、「政府の支出によって景気を下支えするべきだ」と主張した経済学者。
彼の理論は当時、世界中の経済政策に多大な影響を与えました。
MMTもまた政府支出を肯定しているため、「MMT=新ケインズ主義」と混同されがちですが、永濱氏はこの違いを明確に描き出します。
ケインズ経済学とMMTの違い
| 項目 | ケインズ経済学 | MMT |
|---|---|---|
| 注目点 | 有効需要の不足(需要を喚起) | 通貨発行能力(支出の原資) |
| 政府支出の理由 | 景気対策・不況時の乗り切り | 通常時でも有効、供給力の強化 |
| インフレ管理 | 主に税制や金利で調整 | 支出抑制・税制強化でインフレ抑制 |
つまり、ケインズは「使うべきときに使う」、MMTは「使えるなら使うべき」という立場。
この視点の違いが、日本のように長年デフレと低成長に悩む国にとっては大きなヒントになります。
「支出の抑制ではなく、正しい支出の活用」が今求められているのです。
3. 「失われた30年」をどう脱するか?現実に根ざした政策提言
永濱氏の主張の核心は、「財政赤字を恐れすぎた結果、日本は成長のチャンスを逃してきた」という指摘にあります。
1990年代以降、日本は長く続くデフレと経済停滞に悩まされてきました。
少子高齢化、社会保障費の増加、消費税の増税…。
これらは「財政健全化」を名目に正当化されてきましたが、果たして本当に国民の生活は豊かになったでしょうか?
永濱氏は、「プライマリーバランス黒字化」という呪縛から解放されるべきだと説きます。
財政赤字は「問題」ではなく「手段」
MMT的視点に立つと、財政赤字それ自体を悪と見るのではなく、それによって「どんな社会的価値が創出されるか」が重要になります。
たとえば、
- 子育て支援や保育の充実
- 教育費の無償化
- 地方インフラの整備
- 医療や介護への公的投資
こうした施策は短期的には支出でも、長期的には「未来への投資」であり、経済成長の基盤になるのです。
永濱氏の語る“人間中心”の経済政策は、単なる理論を超えて、私たち一人ひとりの暮らしに直結しています。
読後の気づき:経済を「現実」に引き戻す視点
本書を読み終えて最も印象に残ったのは、「経済は人のためにある」という当たり前のことを改めて思い出させてくれたことです。
これまで私たちは「財政赤字は悪」「国の借金は子どもたちの負担になる」と繰り返し聞かされてきました。
しかし、本当にそれだけが真実なのでしょうか?
永濱氏は、MMTを礼賛するのではなく、あくまで冷静に、批判的に、現実に即してその可能性と限界を語っています。
この誠実さが、本書に強い説得力を与えています。
経済学は数字や理論だけではない。
政治や生活、未来へのビジョンと切り離せない「人間の営み」そのものなのです。

まとめ:経済を「恐れず使う」ことで未来が拓ける
『MMTとケインズ経済学』は、経済に苦手意識のある人こそ読むべき一冊です。
- 難解な理論をやさしく紐解き、
- 歴史と現代をつなぐ知の架け橋となり、
- 日本の未来をどうつくるかというビジョンを提示する。
「経済書なのに、こんなにワクワクしながら読んだのは初めて」と感じた読者も多いはずです。
本書は、単なる理論書ではなく、「これからの社会をどう設計するか」を考えるための実践的な道しるべです。
日本経済を変えるのは、政府でも日銀でもなく、経済を正しく理解し、未来に希望を持つ私たち一人ひとりかもしれません。
📗書籍情報
- 書名:MMTとケインズ経済学
- 著者:永濱利廣
- 出版社:ビジネス教育出版社
📚関連おすすめ記事
- 『インデックス投資は勝者のゲーム』感想記事はこちら
- 『9割の負け組から脱出する投資の思考法』レビューはこちら
- 『99%の日本人がわかっていない新・国債の真実』書評はこちら
- 『たった1つの図でわかる!新・経済学入門』感想記事はこちら